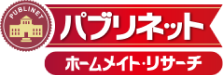消防署情報(冬)
冬の消防署情報/ホームメイト
暮らしの安全を守る消防署では、私たち一般市民の生命を脅かす自然災害への対策は重要視しなければなりません。特に、冬に気を付けなければならないのが、「雪」によって引き起こされる災害や事故。管轄のエリアが思わぬ積雪に見舞われた際に迅速な対応が取れるよう、一部の消防署では雪中訓練を行なっています。ここでは、消防署が行なう雪による被害対策について解説します。
除雪作業

積雪時、消防署では管轄エリア内に点在する消火栓や防火水槽に対して除雪作業を行ないます。消火栓と防火水槽はどちらも、消火活動時に必要となる水を供給する設備です。これら2つの設備が雪に覆われてしまっては、緊急時の消火活動に大きな支障となる恐れがあります。それを防ぐためにも、消火栓と防火水槽の除雪作業は重要な作業と言えるでしょう。また一部の消防署では、一般の方々に対して消火栓と防火水槽の除雪作業を呼び掛けているケースもあります。冬場、特に発生しやすいとされている火事。いざというときの消火作業に支障を来たさないためにも、個人として可能な範囲で除雪作業に協力しましょう。
消防車の雪対策
雪深い地域では、毎年12月を迎える頃に消防車へ雪対策を実施。災害現場への出動時、積雪や路面凍結による交通トラブルが起きては救助活動の妨げとなってしまいます。雪の現場に強い体制を整えるためにも、降雪前に行なう対策は重要だと言えるでしょう。
スタッドレスタイヤへの交換
積雪や凍結などの条件下で、安全な走行を発揮できるスタッドレスタイヤ。冬の災害現場まで安全にたどり着くために、スタッドレスタイヤへの交換は欠かせません。また、スタッドレスタイヤでもカバーできない程の積雪、特に路面凍結が著しい場合を想定して、タイヤチェーンを積み込んでおくところもポイントです。スタッドレスタイヤでも安全には走行できますが、雪道を走る際のパワーはタイヤチェーンが上回ります。ただし、タイヤチェーンは雪が積もった道路以外で走行するとチェーンが切れてしまったり、道路を傷付けてしまったりする恐れがあるため、状況に応じて着脱する必要があります。
スコップ・ポット・チェーンソーの積載
雪深い地域では、消防車にスコップやポットを積載するケースもあります。スコップは雪が積もった災害現場での雪かき用に、ポットは凍結した消火栓のフタを湯で溶かすために用いられます。また普段は難なく通行できる道路も、積雪のため樹木が垂れ下がり通ることができない事態も予測できます。その際、チェーンソーは、通行の妨げになっている枝を伐採し対応することができるのです。わずかな時間に左右される災害現場において、行動をスムーズにするために欠かせない道具と言えるでしょう。
雪中訓練
消火栓と防火水槽の除雪作業、消防車への冬装備を行なったからと言って、雪の災害現場で迅速な行動ができるとは限りません。雪の中では普段通りに活動していてもうまく走れなかったり、ホースを伸ばすことに手間取ったりと、現場のコンディションによっては最大限の力を発揮することができない可能性があります。そのため一部の消防署では雪が積もった際に雪中訓練を行なうことで、どのような現場においても迅速、かつ安全に行動できるように準備をしています。ホースの延長訓練や雪の中での人命救助など、実践を想定した訓練でより対応力の高い組織を作ることが大切だと言えるでしょう。
冬山救助訓練
スキー場が管轄となる消防署では、スキーヤーやスノーボーダーが遭難してしまった場合を想定した、冬山救助訓練が実施されることもあります。探査機として用いられるプローブを使った捜索や、要救助者の掘り出し方法など、冬山救助ならではのスキルが求められます。



火災の多い冬は、消防署の職員も出動回数が増えるシーズンです。火のもとをしっかりチェックして火災予防に努めましょう。また、救急活動も消防署の業務ですが、救命においては初期動作が重要となるため、私たちも救命の知識や対処法を身につけておきましょう。
家庭用消火器点検の日(1月19日)

1月19日は「119」と消防署への電話番号と数字の並びが一緒となることから「家庭用消火器点検の日」に制定されています。火災に備えて自宅に消火器を設置している家庭は、使用期限や消火器が作動するかを点検しておいたほうが良いでしょう。
消火器の点検ポイントは、安全ピンがついているか、操作レバーが変形していないか、容器のサビや変形がないか、ホースのひび割れがないかなどです。また、老朽化した消火器や異常のある消火器を使用すると、破裂などの事故が発生する恐れがあるため、製造年数がどれだけ経過しているか確認し、5年経過しているのであれば、消火器に封入されている消火剤を詰め替えるようにしましょう。古い消火器の処分は、リサイクルシールがあるものについては、消火器を販売するショップに持ち込めば、無料で回収してくれます。
これら家庭用消火器には、「粉末タイプ」、「強化液タイプ」、「エアゾールタイプ」、「投入タイプ」の4種類があり、「粉末タイプ」と「強化液タイプ」は、一般的な消火器に近いタイプで、火元に直接吹きかけます。1m程度の炎でも、きちんと吹き付ければ鎮火させることができます。「エアゾールタイプ」は片手で操作でき手軽に消火ができますが、大きな炎には消火しきれない場合があり、キッチンなどの小規模火災用と考えたほうが良いでしょう。「投入タイプ」は消火液の入った容器をそのまま投げつけて消火をするタイプで、子どもでも使用でき、避難通路を確保するときに便利です。置き場所に合わせて最適なタイプの消火器を設置するのが望ましく、それぞれ1年に1回は点検するようにしましょう。
消防服
消防職員は様々な状況で活動するため、目的や状況に応じた服装を着用します。事務系や立ち入り検査などでは「制服」を着用し、冬はシャツと上着、夏はシャツが制服となります。消防士が通常着ている服は「作業服」で、動きやすく機能性に優れており、夜勤などで寝るときも作業服を着たまま寝ます。救助する場合は「救助服」を着用し、救助のスペシャリスト・レスキュー隊の隊員が着用します。消防士が火事の現場で着用するのは「防火服」と言い、火に近づけるように耐火性のある厚手の服を着用。防火服以外にも、ヘルメットや長靴、空気呼吸気を装備し、すべて装備すると約10kgの重さにもなります。このため、レスキュー隊は日々体力をつけるための訓練を行なっています。また、特殊な化学薬品や放射能汚染、テロでの災害時には、体が外気と接触しないように完全密封した「化学防護服」や「耐熱服」を着用し、体の安全を守りながら作業を実施します。
救急車に乗り込む「救急救命士」は、「救急服」を着て救急処置に当たります。消防士より高度な救急処置ができるよう、消防士と制服を分けています。また、感染症の患者を扱う場合には、「感染防止衣」と手袋、ゴーグル、マスクなどをつけて、感染症にかからないように防ぎます。この他に、水難救助の場合は「ウェットスーツ」あるいは「ドライスーツ」を着て、海や河川、湖沼などで救助をしたり、人の捜索をします。消火活動や救助活動では、スピーディーな対応が求められるため、目的や状況に応じた消防服が効果を発揮します。
AED講習会
最近は至るところに設置されるようになった「AED(自動体外式除細動器)」ですが、実際に使ったことがある人は、まだ少ないのではないでしょうか。各消防本部では、「救命講習会」を開催して、AEDの使用方法を市民に広く伝えています。AEDは、心臓病などで突然倒れた人に対して、電気ショックを与え、心臓の働きを取り戻すための医療機器で、救命の初期動作として大きな役割を担っています。万一の事態が起きたときに、誰でもすぐに使用できるようになっており、公共施設をはじめ、交通機関や商業施設など、多くの人が集まる場所にはほとんど設置してあります。
冬の季節は日中と夜間で寒暖の差があり、心臓に持病がある人や高齢者の中には、不調を訴える人も増えてくる時期です。万一の時に備えてAED講習会に参加し、AEDを実際に使用した救命方法をを覚えておきましょう。
冬は空気が乾燥することから、火災が発生しやすいシーズンです。正しい知識を身につけて、防火を心がけましょう。また、新年になると消防署の恒例行事である「出初め式」が開催されます。これも、一人ひとりが火の扱いに注意して、火事を起こさないよう防災意識の向上を目的に開催されています。
火災を予防しよう

冬になると火事のニュースをよく耳にするようになります。これは、暖房などで火を使う機会が増え、空気も乾燥していることから、火災が発生しやすくなるためです。出火原因で常に上位になるのが、「コンロ」、「タバコ」、「ストーブ」、「放火」による火災です。
コンロ火災の原因は主に火の消し忘れで、ちょっと目を放した間に近くのものにコンロの火が引火するケースや天ぷら油による火災です。料理をするときはその場を離れないようにするか、火を消してからその場を離れましょう。また、カーテンや紙など燃えやすいものを、コンロの近くに置かないことが基本です。
タバコによる出火は、ほとんどが火の不始末が原因です。寝タバコで火が十分に消えていないうちに、他の吸い殻などに火が燃え移ったり、火が残ったままゴミ箱に投げ捨てて紙くずなどに引火するのが火災の原因となります。まず、タバコの火をしっかり消すことと、消えたことを必ず確認することが大切です。また、灰皿に吸い殻をためないようにしたり、燃えやすいものを近くに置かないなど、吸うときのルールを作って徹底しましょう。
ストーブによる出火は高齢者に多く見られ、石油ストーブ・石油ファンヒーターの上に洗濯物を干したり、キャップをしっかり閉めなかったことによる灯油のモレなど、ちょっとした不注意によって火災になるケースが目立ちます。また、石油などに引火すると大惨事に繋がるので、取り扱いには十分注意が必要です。ストーブを使うときは、回りに燃えやすいものを置かないこと、使い終わったら消火を確認すること、給油するときは必ず火を消すことが重要です。また、使用するときも誤って倒したりしないように配置場所にも気を使いましょう。
放火による火災は、自分たちの不注意ではないため完全には防げませんが、家の周りを整理整頓し、古新聞や灯油缶など放火されないようにしておくことが必要です。
この他に、住宅用火災警報器を設置したり、寝具やカーテンに不燃素材を使うなど、普段から防災意識を持って、大切な家族や財産を守るようにしましょう。
出初め式

消防署の新年恒例行事と言えば「出初め式」があります。これは消防関係者の仕事始めの行事で「消防出初め式」とも言います。各市町村の消防署員や消防団員が、はしごに乗ってパフォーマンスを披露したり、木遣り歌などを歌うなど、昔ながらの伝統技能を披露します。また、一斉放水や消防演習、消防車のパレードも行なわれます。かつては1月4日に行われていましたが、今は1月6日に実施するのが恒例となっています。
江戸時代、江戸の町で火事が多く発生したことから、江戸幕府によって「火消」と言う消防組織が制度化されました。その後1657年に起こった「明暦の大火」では、江戸城天守閣を含む江戸の大半が焼失し、数万人の犠牲者を出す大災害となりました。幕府はこれを重んじ、幕府直轄の新たな消防組織「定火消」を制度化し、1659年1月4日に「定火消」4組が上野東照宮に集結し気勢をあげました。これが「出初め式」の始まりとされています。これ以降、毎年1月4日に出初が行なわれるようになり、次第に儀式となっていきました。やがて鳶職(とびしょく)の派手な装束をまとい、梯子(はしご)の曲乗りが行なわれるようになり、大衆の注目を浴びるようになりました。享保年間になると、町人による消防組織「町火消」が成立し、「いろは組」48組と、東の本所・深川を担当する16組の「火消組合」が設けられました。町火消にも新年に定火消が行なっていた出初の慣習が継承され、それぞれの組を表す纏(まとい)を掲げて組内の町を練り歩いたり、梯子乗りや木遣り歌を披露したりしました。
明治維新後は、火消はすべて廃止され、新政府によって「火災防御隊」という消防組織が設置されました。1874年に東京警視庁が設けられたことによって、消防組織はその所属となり、翌1875年には東京警視庁練兵場に消防組織全員が集まって、第1回東京警視庁消防出初め式が開かれました。これが、現在行われている東京消防出初め式の起源となっています。
戦後の1947年には、各市町村が任意に設置する消防団が誕生し、翌1948年に「消防組織法」と「消防法」が制定され、消防は各市町村が管理することになりました。出初め式も各市町村の消防団員に受け継がれ、音楽隊の演奏やパレードなども加わり、新春イベントとして定着しています。